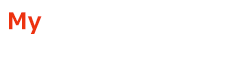解約返戻金の仕組みと受け取り方:生命保険の解約時に知っておくべきポイント

生命保険の解約返戻金は、契約を途中で解約した際に受け取れるお金のことです。
しかし、その仕組みや計算方法、税金の扱い、さらには解約手続きに関する注意点など、詳細を理解していないと損をする可能性があります。
特に、解約返戻金の有無は保険の種類によって異なり、契約時にしっかり確認することが重要です。
本記事では、解約返戻金の基本から、税金、解約時の手続き、シミュレーションの活用方法、さらには活用ケースや資金計画への影響など、幅広く解説していきます。
生命保険を見直す際の参考にしてください。
\勧誘無し!マイプラザなら、無料で保険の相談&見積が可能!/
生命保険の解約返戻金とは何か
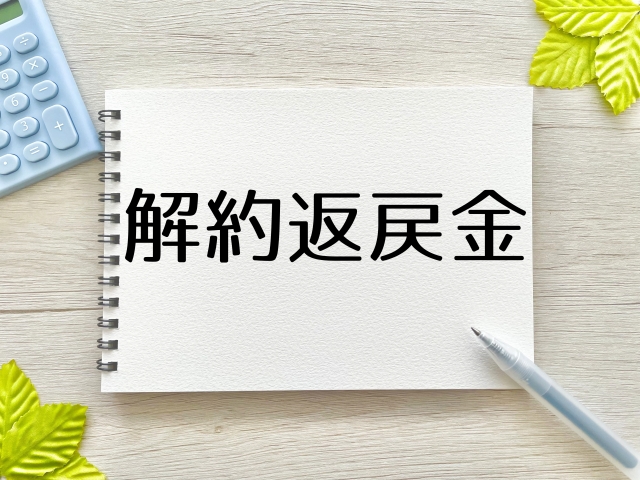
生命保険の解約返戻金とは、保険契約を途中で解約した際に受け取れる金額のことを指します。
しかし、すべての生命保険に解約返戻金があるわけではなく、また受け取れる金額も契約内容や経過年数によって異なります。
この章では、解約返戻金の基本的な仕組みや計算方法、解約返戻金がない保険について詳しく説明していきます。
解約返戻金の基本的な仕組み
生命保険の解約返戻金は、契約者が保険料を一定期間支払った後に、保険を解約した際に戻ってくるお金です。
これは主に貯蓄型の生命保険に適用され、掛け捨て型の保険では基本的に発生しません。
解約返戻金が支払われる仕組みは、支払った保険料の一部が積み立てられ、保険会社が運用することで増えるというものです。
ただし、解約するタイミングによっては、支払った保険料よりも受け取れる金額が少なくなることもあります。
特に、契約後の早い段階で解約すると、解約返戻金はほとんどないか、あっても非常に少額です。
これは、保険会社が契約者の保障を確保するために、初期費用として一定額を差し引くためです。
一方、長期間契約を維持すれば、解約返戻金は増加し、場合によっては支払った保険料を上回ることもあります。
また、解約返戻金は、保険商品によって「低解約返戻金型」や「無解約返戻金型」などの異なる仕組みを持つことがあります。
低解約返戻金型は、一定期間内の解約時には通常より少ない返戻金しか受け取れませんが、その分保険料が安く設定されています。
一方、無解約返戻金型は、解約返戻金が発生しない代わりに、より低コストで保障を受けられる点が特徴です。
このように、生命保険の解約返戻金は契約内容やタイミングによって大きく変動するため、契約時に十分な確認が必要です。
解約返戻金の計算方法について
解約返戻金の金額は、契約している生命保険の種類や契約期間、支払った保険料の総額などによって決まります。
一般的に、解約返戻金は「払込保険料の累計額」と「解約返戻率」を掛け合わせた金額として算出されます。
解約返戻率は、契約の経過年数に応じて変動し、長期間契約を続けるほど高くなる傾向があります。
例えば、契約から10年未満で解約すると、解約返戻率が低いため、支払った保険料よりも少ない金額しか戻ってこないことが一般的です。
逆に、契約から20年以上経過すると、解約返戻率が100%を超えるケースもあり、支払った保険料を上回る解約返戻金を受け取れることがあります。
このため、解約のタイミングは慎重に考える必要があります。
また、解約返戻金の計算には、以下のような要素も関係してきます。
- 契約年数:解約時点での契約年数が長いほど、解約返戻率が上がる傾向があります。
- 保険料の払込方法:月払い、年払い、一括払いなどの違いによって、積み立てられる金額が変わる場合があります。
- 契約している保険の種類:終身保険や養老保険など、契約の種類によっても返戻率が異なります。
なお、具体的な解約返戻金の金額は、保険会社が提供する「解約返戻金試算表」やシミュレーションツールを利用することで確認できます。
契約者専用のウェブサイトやカスタマーサービスを通じて詳細な金額を知ることも可能です。
解約返戻金の計算方法を理解し、適切なタイミングで解約を検討することが、損をしないための重要なポイントとなります。
解約返戻金がない保険の種類
生命保険の中には、途中で解約しても解約返戻金が発生しないものがあります。
これらの保険は「掛け捨て型」と呼ばれ、保障を重視した設計になっているのが特徴です。
契約者が一定期間にわたり保険料を支払うことで保障を受ける仕組みであり、契約期間が終了すると保障はなくなります。
以下、代表的な解約返戻金がない保険の種類を紹介します。
定期保険
定期保険は、一定期間のみ保障が続くタイプの保険で、多くの場合、解約返戻金はありません。
例えば、「10年間の定期保険」に加入した場合、10年間は保障が継続しますが、その後は更新しない限り保険契約が終了します。
定期保険のメリットは、同じ保障額の終身保険に比べて保険料が割安であることです。
そのため、比較的安価に大きな保障を確保したい人に向いています。
収入保障保険
収入保障保険は、契約者が亡くなった場合に、残された家族が毎月一定額の給付金を受け取れる保険です。
この保険も掛け捨て型であり、途中で解約しても解約返戻金は発生しません。
ただし、万が一の際に遺族の生活費を補うのに適した保険であるため、貯蓄性よりも保障を重視したい人におすすめです。
医療保険・がん保険
医療保険やがん保険も基本的に掛け捨て型であり、解約しても返戻金はありません。
これらの保険は、病気やケガをした際の入院・手術費用をカバーすることを目的としているため、貯蓄性は考慮されていません。
ただし、一部の医療保険には「払戻金付き」タイプがあり、一定期間契約を継続した場合に一部の保険料が戻ってくるものもあります。
無解約返戻金型終身保険
通常の終身保険には解約返戻金がありますが、無解約返戻金型終身保険は、解約した際の返戻金をゼロにする代わりに、保険料を安く設定した商品です。
このタイプは、死亡保障を目的としており、「解約せずに最後まで保障を維持する」ことを前提としています。
解約返戻金がない保険は、貯蓄性がない代わりに、比較的安い保険料で高い保障を受けられるメリットがあります。
目的に応じて、必要な保障とコストのバランスを考慮しながら選ぶことが重要です。
\ファイナンシャルプランナーが、あなたの人生設計を無料でサポート!/
解約返戻金の税金とその影響
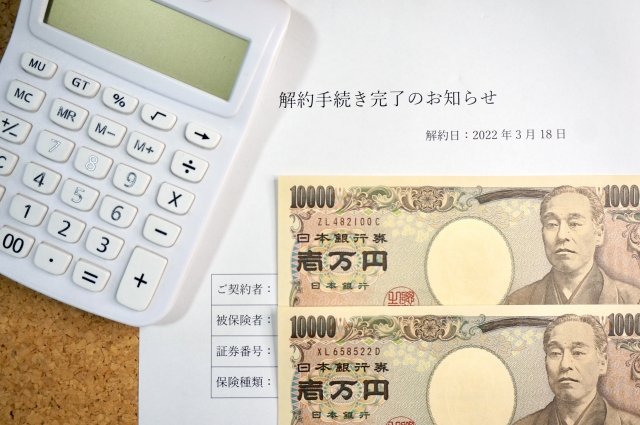
生命保険の解約返戻金を受け取る際、税金が発生する場合があります。
特に、解約返戻金が支払った保険料の総額を超えた場合、その超過分は課税対象となります。
本章では、解約返戻金の課税対象となる条件や税金の計算方法、確定申告の必要性について詳しく解説します。
解約返戻金にかかる税金の仕組み
生命保険の解約返戻金が課税対象になるかどうかは、受け取った金額と支払った保険料の総額の差額によって決まります。
基本的な考え方は以下の通りです。
- 支払った保険料の総額以下の解約返戻金 → 税金はかからない(元本の払い戻し扱い)
- 支払った保険料の総額を超えた解約返戻金 → 超過分が「一時所得」として課税対象
つまり、保険料を300万円支払っていた場合、解約返戻金が300万円以下なら税金は発生しません。
しかし、解約返戻金が400万円になった場合、超過分の100万円が課税対象になります。
一時所得としての扱いと計算方法
解約返戻金の利益部分(解約返戻金 - 支払った保険料総額)は「一時所得」として扱われます。
一時所得には50万円の特別控除が適用され、さらに課税対象額は半額に軽減されます。
計算方法は以下の通りです。
(解約返戻金 - 支払った保険料総額 - 特別控除50万円)÷ 2 = 課税対象額
具体例
- 支払った保険料の総額:250万円
- 解約返戻金:350万円
- 利益部分(350万円-250万円):100万円
- 控除後の金額(100万円-50万円):50万円
- 課税対象額(50万円 ÷ 2):25万円
この「課税対象額」は、他の所得と合算され、所得税や住民税の計算に反映されます。
一時所得のメリットと注意点
- 特別控除があるため、利益部分が50万円以下であれば課税されない
- 課税対象額は半分になるため、他の所得と比べて税負担が軽い
- ただし、一時所得が増えると翌年の健康保険料や扶養控除に影響を与える可能性がある
確定申告の方法と注意点
解約返戻金による一時所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
会社員や公務員であっても、該当する場合は確定申告を行わなければなりません。
確定申告の必要条件
次のいずれかに該当する場合、確定申告が必要です。
- 一時所得の課税対象額が20万円を超える(特別控除適用後の額)
- 他の所得と合算し、総所得額が増えることで税額が変わる
申告の手順
① 必要書類の準備
- 保険会社から送られる「解約返戻金の支払い通知書」
- 保険料の支払い証明書
- 給与所得者の場合は源泉徴収票
② 申告書の作成
- 国税庁のウェブサイトや税務署で確定申告書Bを入手し、一時所得の欄に記入
- e-Taxを利用すればオンライン申請も可能
③ 申告書の提出と納税
- 申告期間は毎年2月16日~3月15日(翌営業日まで延長されることもあり)
- 所得税が発生する場合、期日までに納税が必要
確定申告の注意点
- 申告漏れを防ぐ:20万円を超える場合は必ず申告を
- 翌年の健康保険料への影響:所得が増えると保険料も増額される可能性あり
- 扶養控除の適用条件を確認:一時所得が増えることで、扶養控除の適用外になる場合がある
適切な申告を行い、不要な税負担を回避するために、解約前にしっかりとシミュレーションすることが大切です。
\結婚・転職・出産……ライフステージが変わったら、マイプラザで無料相談を!/
解約時の手続きと注意事項

生命保険を解約する際には、手続きの流れやタイミングを慎重に検討する必要があります。
特に、解約のタイミングによっては返戻金の金額が大きく変わることもあるため、事前に十分な確認が欠かせません。
本章では、解約の影響や手続きの流れ、受け取る金額について詳しく解説します。
解約のタイミングとその影響
生命保険を解約するタイミングによって、受け取れる解約返戻金の金額が大きく異なります。
特に、契約期間が短い場合や、一定期間が経過する前に解約すると、返戻金がほとんど受け取れない場合もあります。
早期解約のリスク
多くの生命保険では、契約から一定期間(一般的には10年以内)の解約では、支払った保険料の総額よりも大幅に少ない返戻金しか受け取れません。これは、契約初期の保険料の多くが保険会社の運営費や保障費用に充てられているためです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 契約から3年以内に解約:解約返戻金はほとんどない、またはゼロ
- 契約から10年経過後に解約:払い込んだ保険料の約60%~80%程度の返戻金を受け取れる
- 契約満期近くでの解約:払込保険料を上回る解約返戻金を受け取れることもある
解約に適したタイミングの判断
解約を検討する際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 返戻率の確認:解約時にどの程度の金額を受け取れるか、保険会社のシミュレーションを利用して確認する
- 税金の影響:解約返戻金の額が大きいと、所得税・住民税・健康保険料に影響するため、最適なタイミングを考慮する
- 保障の代替策:解約後の医療・死亡保障の代替手段を検討する(新たに加入できるか、他の貯蓄手段で補えるか)
特に、貯蓄型の保険は「解約しないほうがメリットが大きい」ケースもあるため、他の選択肢(払い済み保険への変更など)も考慮するとよいでしょう。
必要な書類と手続きの流れ
生命保険を解約する際には、必要な書類を揃えた上で、保険会社の指定する手続きを進める必要があります。
解約の種類によって手続きが異なる場合もあるため、事前にしっかりと確認しましょう。
解約手続きに必要な書類
生命保険の解約には、以下のような書類が必要となることが一般的です。
- 契約者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 保険証券(契約時に発行されたもの)
- 解約請求書(保険会社から取り寄せる、またはオンラインでダウンロード)
- 振込口座の情報(解約返戻金の受取先)
- 印鑑(必要な場合)
保険会社によっては、これ以外に追加の書類が求められることもありますので、事前にカスタマーセンターなどで確認しておくとスムーズです。
解約手続きの流れ
生命保険の解約手続きは、以下のような流れで進めます。
① 保険会社に解約の意思を伝える
- 契約している保険会社の窓口、担当者、またはコールセンターに連絡し、解約の申し出を行う。
- 返戻金の試算や、解約に伴う影響(税金、保障の消失など)について説明を受ける。
② 必要書類を準備し、提出する
- 保険会社から解約請求書を取り寄せ、必要事項を記入。
- 併せて、本人確認書類や保険証券などを揃える。
③ 書類審査・手続きの完了
- 保険会社が書類を確認し、不備がなければ解約手続きを進める。
- 手続き完了までの期間は、通常1週間〜2週間程度。
④ 解約返戻金の振込
- 手続きが完了すると、指定した口座に解約返戻金が振り込まれる。
- 振込日については、保険会社ごとに異なるため事前に確認しておくとよい。
解約手続きの注意点
- 書類の記入ミスを防ぐ:記入漏れや印鑑の不備があると、手続きが遅れることがあるため、慎重に確認する。
- 解約請求の期限を確認:一部の保険では、解約請求の期限が定められている場合がある。
- ネットでの解約が可能かチェック:最近では、オンラインで解約手続きを完了できる保険も増えているため、利用できる場合は活用すると手続きがスムーズになる。
保険の解約は慎重に行い、手続きの遅れやトラブルを防ぐためにも、必要な書類をしっかり準備しておきましょう。
解約後に受け取る金額の留意点
生命保険を解約した際に受け取る解約返戻金には、いくつかの留意点があります。
解約時の金額は、契約内容や保険の種類、解約のタイミングによって大きく異なるため、事前に正確な見込みを立てておくことが重要です。
本節では、解約返戻金の額に影響を与える要因や注意すべきポイントについて解説します。
解約返戻金の金額の決まり方
解約返戻金の金額は、契約時に支払った保険料や保険の種類、解約時点での経過年数によって決まります。特に以下のポイントが影響します。
- 契約期間:契約から経過した年数が短いと、解約返戻金が少なくなる場合があります。特に、契約初期に解約すると支払った保険料に対して返戻金が少ないことが一般的です。
- 保険の種類:終身保険、養老保険、定期保険など、それぞれの保険の返戻金の仕組みが異なります。貯蓄型の保険では、支払った保険料に対して返戻金が多くなる傾向があります。
- 特約の有無:特約が付帯されている場合、その特約内容によって解約返戻金に影響が出ることがあります。
解約返戻金の受け取り方法
解約返戻金の受け取り方法には、一般的に以下の2つがあります。
- 一括受け取り:解約返戻金を一度に全額受け取る方法です。受け取り後、すぐに現金として手に入るため、急な資金が必要な場合に有効です。
- 分割受け取り:返戻金を複数回に分けて受け取る方法です。長期的な生活資金を見込んで受け取る場合や、税金面での負担を軽減するために利用されることがあります。
受け取り方法は、保険契約の内容や契約者のニーズによって選択できる場合があるため、解約前に保険会社に相談すると良いでしょう。
解約返戻金が少ない場合の対策
解約返戻金が期待したよりも少ない場合、以下のような対策を考慮することができます。
- 払い済み保険に変更する:解約せずに、払い済み保険に変更することで、今後の保険料の支払いが不要になる一方、保障は一定程度維持できる場合があります。この方法を選ぶと、解約返戻金は少なくなりますが、将来の保障を確保できる利点もあります。
- 契約の継続や追加の見直し:解約返戻金が少ない場合でも、今後の保障内容や契約条件を見直し、必要に応じて契約を継続する選択肢もあります。
解約後の税金負担に注意
解約返戻金には税金がかかる場合があるため、受け取る金額に対する税負担も考慮する必要があります。
解約返戻金が一時所得として扱われるため、確定申告が必要になることもあります。
解約前に税金の影響を把握し、解約後にどれだけの金額が実際に手元に残るのかを確認しておくことが重要です。
\取り扱い保険多数!代理店だからこそ、あなたにぴったりの保険が見つかる◎/
生命保険の種類別解約返戻金

生命保険の種類によって解約返戻金の仕組みや金額は異なります。
保険の種類ごとに特徴を理解しておくことが、解約時に最適な判断を下すために重要です。
本章では、主な生命保険の種類ごとに解約返戻金について解説し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく紹介します。
終身保険の解約返戻金について
終身保険は、契約者が生存している限り保障が続き、解約返戻金が支払われるタイプの保険です。
一般的に、契約期間が長ければ長いほど、解約返戻金の金額が増加します。
解約返戻金の特徴
終身保険では、解約時に受け取る返戻金は保険料の積立部分が元となります。
積立部分は保険料の一部が運用され、利益を生み出します。
そのため、長期間契約を続けることで解約返戻金が大きくなる仕組みです。
- 長期契約における返戻金:契約から10年以上経過した場合、払込保険料を上回る解約返戻金が期待できることが多い
- 初期の解約返戻金:契約から数年以内に解約した場合、支払った保険料を下回る解約返戻金しか受け取れないことがある
終身保険のメリット
- 保障が一生涯続く:契約者が亡くなるまで保障が続き、解約返戻金も生涯の保障に対する貯蓄として機能する
- 税制優遇:解約返戻金の一部は一時所得として課税されるが、長期契約によって課税額を抑えられる可能性がある
終身保険のデメリット
- 短期間での解約時の返戻金が少ない:契約初期に解約すると、ほとんど返戻金が得られない
- 保険料が高額:保障内容が手厚いため、他の保険に比べて保険料が高く設定されることが多い
養老保険の特徴と返戻金
養老保険は、契約者が一定年齢(通常は60歳や65歳)に達した時に満期返戻金を受け取るタイプの保険で、死亡保障と貯蓄機能を兼ね備えています。
満期時に受け取る返戻金は、支払った保険料を上回ることが多いですが、解約時の返戻金は契約年数によって異なります。
解約返戻金の特徴
養老保険では、満期返戻金が最も高く、契約者が満期を迎えた時点で受け取ることができます。
解約返戻金は、満期返戻金と比較して少ないことが多いですが、解約時に一定の額を受け取ることができます。
- 満期時の返戻金:支払った保険料の総額を上回る返戻金が得られることが多い
- 解約時の返戻金:契約から一定年数が経過している場合でも、解約返戻金は満期返戻金よりも少ない
養老保険のメリット
- 満期返戻金が期待できる:満期時に高額な返戻金を受け取れるため、貯蓄型の保険としての役割を果たす
- 死亡保障も確保できる:契約者が満期を迎えられなかった場合でも、死亡保障として返戻金が支払われる
養老保険のデメリット
- 解約返戻金が少ない:契約から早期に解約した場合、支払った保険料に対して解約返戻金が少ない
- 保険料が高額:保障と貯蓄機能が併用されているため、保険料が高く設定されることが多い
学資保険とその解約返戻金
学資保険は、子供の教育資金を準備するための保険で、契約者が指定した年齢(通常は18歳や22歳)になると、満期返戻金が支払われます。
学資保険は、基本的に契約者が生存している限り、教育資金を確実に準備できるメリットがありますが、解約返戻金には特有の特徴があります。
解約返戻金の特徴
学資保険の解約返戻金は、契約者が契約から一定期間を経過した場合に支払われます。
特に、契約期間が長くなると解約返戻金が増える傾向がありますが、契約期間が短いと、解約返戻金は支払った保険料に対して少ないことが多いです。
- 解約返戻金が低い場合:契約開始から数年以内に解約した場合、ほとんど返戻金がないことが多い
- 満期返戻金:子供が大学進学時に必要な資金が準備されるため、解約返戻金は期待できます
学資保険のメリット
- 教育資金を確保できる:解約返戻金は子供の教育資金に使える
- 契約者が亡くなった場合も保障される:契約者が亡くなった場合でも、満期時の返戻金は支払われる
学資保険のデメリット
- 解約返戻金が少ない場合がある:契約期間が短い場合や途中で解約すると、期待する返戻金を受け取れないことがある
- 途中解約のハードルが高い:解約しても返戻金が少ない場合、継続するほうが有利となることが多い
\勧誘無し!マイプラザなら、無料で保険の相談&見積が可能!/
払戻金の受け取り方

生命保険を解約した際や契約に基づく払戻金を受け取る際には、受取人の設定や払戻金の種類など、いくつか注意すべき点があります。
本章では、払戻金の受け取りに関連する重要なポイントについて詳しく説明します。
受取人の設定とその条件
生命保険の払戻金を受け取る際には、事前に受取人を設定しておく必要があります。
受取人には、主契約者の家族や指定した個人を設定することが一般的です。
受取人を指定する際には、契約時の確認書類や契約変更手続きが必要となる場合があります。
受取人の設定には以下のような条件があります:
- 契約時の受取人設定:契約時に指定した受取人が優先される
- 変更手続き:受取人を変更したい場合は、保険会社への手続きが必要で、受取人変更の通知や書類の提出が求められる
- 受取人の権利:受取人には、契約者が亡くなった際に保険金を受け取る権利が与えられ、指定された人物以外が受け取ることは基本的にありません
払戻金の種類とその意味
払戻金は、保険の種類や契約内容により異なります。主に以下の種類に分けられます。
- 解約返戻金:契約者が保険を解約した際に受け取る金額。長期的な契約者には通常多くの返戻金が支払われるが、初期の解約時には少額となることが多い
- 満期保険金:満期を迎えた際に支払われる保険金。契約内容によって満期時に受け取る額が異なり、貯蓄型保険などで見られる
- 死亡保険金:契約者が死亡した際に受け取る金額。遺族に対する保障として支払われる
- 特約の払い戻し金:特約に基づく払い戻し金で、特定の事象(例えば病気や事故)が発生した際に支払われることがある
払戻金は、契約内容や契約者のライフステージによって選択肢が異なるため、保険に加入する前に十分に理解しておくことが大切です。
受け取った後の資金運用
受け取った払戻金をどのように運用するかは、今後の生活設計に大きく影響します。
払戻金を受け取った後は、以下のような資金運用の選択肢が考えられます。
- 貯蓄や定期預金:安定した運用方法として、預金に回すことが考えられます。低金利の現在ではあまり高いリターンは期待できませんが、安全性が高いです
- 投資信託や株式:リスクを取って資産を増やしたい場合は、投資信託や株式などへの投資が選択肢になります。リスクを管理しつつ、将来に向けて資産を運用できます
- 年金や保険商品:払戻金を年金形式で受け取ることが可能な保険商品もあり、将来の年金として活用することもできます
資金運用の選択肢をしっかりと理解し、ライフプランに合った使い方を考えることが重要です。
\ファイナンシャルプランナーが、あなたの人生設計を無料でサポート!/
解約返戻金に関するよくある質問

解約返戻金に関しては多くの質問が寄せられます。
特に、どのような場合に解約返戻金が発生するのか、解約時の手続きや税金の取扱いについては、契約者が不安に感じることが多いポイントです。
本章では、解約返戻金に関するよくある質問を取り上げ、その回答を説明します。
契約者が知っておくべきポイント
解約返戻金に関して契約者が知っておくべき基本的なポイントは以下の通りです。
- 解約返戻金は契約内容により異なる:解約返戻金の額は、保険の種類や契約年数によって異なります
- 早期解約は返戻金が少ない:特に契約初期に解約すると、支払った保険料より少ない額の返戻金になることが多い
- 満期まで契約を続けると、返戻金が増える:長期間契約を続けることで、保険料の積立部分が増え、解約返戻金が増加する
解約時の疑問とその回答
解約返戻金に関連する疑問としてよく挙げられるのが、解約時にどれくらいの返戻金が支払われるか、また解約後の対応についてです。
- 解約返戻金を受け取るタイミング:通常、解約手続きが完了してから1〜2週間程度で返戻金が支払われます
- 返戻金が少ない場合の対策:もし解約返戻金が少ない場合、契約内容の見直しや払い済み保険への変更を検討することができます
保険会社の対応について
解約時に保険会社がどのように対応するかについての心配もよくあります。
保険会社は、解約手続きや返戻金に関する案内を迅速に行うことが一般的ですが、契約内容や規約によって手続きの詳細が異なる場合もあります。
- 事前の確認が重要:解約手続きや返戻金について不明点がある場合、事前に保険会社に問い合わせて確認しておくとスムーズに進められます
- オンライン手続き:最近では、インターネットを通じて解約手続きを行える場合もあるため、手続き方法を確認しておきましょう
\結婚・転職・出産……ライフステージが変わったら、マイプラザで無料相談を!/
まとめ
生命保険の解約返戻金は、契約内容や解約のタイミング、契約期間によって大きく異なります。
解約返戻金を受け取るには、契約者としていくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
解約後には、受け取った金額をどのように運用するかも大切な決断となります。
また、解約時には税金の影響を考慮し、必要な手続きを確実に進めることが求められます。
これらの情報を元に、賢い解約と資金運用を行い、将来に備えることが大切です。
\取り扱い保険多数!代理店だからこそ、あなたにぴったりの保険が見つかる◎/